【PR】本ブログ記事には広告を含む場合があります。
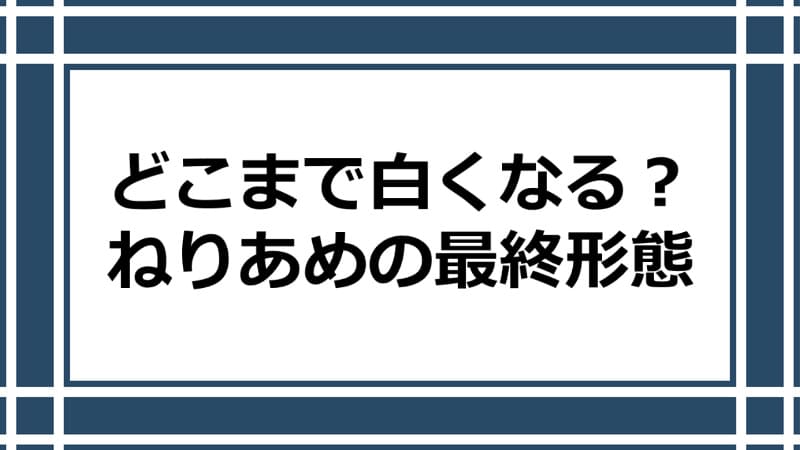
懐かしい駄菓子、ねりあめ。棒でくるくると練ると、色や硬さが変わっていく不思議なお菓子です。子どもの頃、夢中で練って遊んだ記憶がある方も多いのではないでしょうか。
実はこのねりあめ、ただの駄菓子ではありません。江戸時代に生まれた伝統的な製法、水飴との違い、そして練ることで白くなる秘密など、知られざる魅力がたくさん詰まっているのです。
この記事では、そんなねりあめの奥深い世界を歴史から栄養価、そして最終形態まで徹底的に解説します。

さあ、あなたも一緒にねりあめの魅力を再発見してみませんか?(笑)
ねりあめってどんな飴?水飴との違いを解説

ねりあめは駄菓子屋さんなどで売られている、粘り気のある甘い飴菓子です。 蜂蜜よりも少し強い粘り気があり、様々な色があります。
ねりあめは、そのまま舐めると軟らかすぎて垂れてしまうため、箸などで練って空気を含ませ、ある程度硬くなってから食べるのが一般的です。
しかし必ずしも練ってから食べる必要はなく、そのまま舐めて楽しむこともできます。 その場合は、柔らかくて垂れやすいので注意が必要ですよ。
ベタベタするのを防ぐため、オブラートに包んで売られていることもあります。 子供の頃、ねりあめを練って遊んだ記憶が蘇ってくる方もいるのではないでしょうか。

ねりあめは日本の伝統的な駄菓子として、懐かしい思い出と結びついていますね。
ねりあめの歴史
ねりあめの歴史は江戸時代に遡り、当時の菓子料理書に紹介された「堅飴」の製法が原型とされています。
さらに古くは奈良時代に米を原料とした「醴飴」が貴族に珍重され、鎌倉時代に中国から砂糖が伝来すると砂糖を使った飴作りが始まりました。
江戸時代には砂糖の生産が盛んになり、庶民にも飴が普及。堅飴の製法が確立され、ねりあめが誕生したのです。
ねりあめと水飴の違い
ねりあめと水飴はどちらも甘いお菓子ですが、材料や製法、用途に違いがあるんです。
ねりあめは砂糖と水飴を主原料としています。 これらを煮詰めて練り上げることで作られます。一方の水飴は、でんぷんを麦芽で糖化させて作られます。
水飴の原料となるでんぷんには、米、トウモロコシ、ジャガイモなど、様々な種類があります。

ねりあめ特有の「練り」の工程は、飴に空気を含ませ、独特の白さと食感を生み出すために欠かせません。
この練る工程によって、ねりあめは水飴に比べてより滑らかで、噛み応えのある独特の食感になります。
用途の違い
ねりあめは主に駄菓子としてそのまま食べられます。 一方の水飴は、お菓子の材料や調味料として幅広く使われます。 例えば、水飴はあんこや飴細工、煮物などに使われます。
またねりあめも、ババロアなどのデザートに風味やコクを足すために使われる場合があります。
ねりあめが白くなる秘密
ねりあめを練ると白くなるのは、なぜでしょうか? それは練ることで飴のなかに空気が含まれるからです。
最初は透明なねりあめですが、練ることで小さな気泡が飴のなかにたくさん入り込みます。そしてその気泡に光が乱反射することで、白く見えるようになるのです。
ねりあめの練り方
ねりあめは、付属の2本の棒を使って練るのが一般的です。 蜂蜜よりも粘度が高いねりあめを棒で練って空気を含ませることで、食べやすい硬さになりますよ。
白くなる速度と関係する要因
ねりあめが白くなる速度は、以下の要因に影響されます。
■温度
温度が高いほど飴が柔らかくなり、空気が含まれやすいため、白くなる速度が速くなります。
■湿度
湿度が高いと飴が湿気を吸って柔らかくなり、白くなる速度が速くなります。
■練り方
力強く練ると空気が多く含まれるため、白くなる速度が速くなります。
- 実際に練って確かめてみよう! おすすめの「ねりあめ」はコチラ
- 「ねりあめ」が白くなる不思議な変化や、水飴との食感の違い、分かっていただけましたか? この面白い変化を、ぜひご自身の手で体験してみてください。
昔懐かしい駄菓子屋の味を再現できるセットなら、お子さんと一緒に科学実験のように楽しむこともできますよ。懐かしの味と驚きを、ぜひご家庭で。
>> Amazonで「懐かしのねりあめ」を探す
ねりあめの栄養価
ねりあめは、砂糖を主原料としているため主な栄養素は糖質です。 水飴も同様に糖質が主成分です。 そのため、食べ過ぎには注意しましょう。
ねりあめの最終形態とは?
ねりあめの最終形態は飴を練り続けることで白く変化し、空気を含んで硬くなった状態です。
最初は透明感のある飴ですが、付属の棒などで練っていくうちに空気を含んで白っぽく変化し、粘度が増してきます。変化の過程は次の動画がわかりやすいですよ。
@uryo1113 ねり飴ってやったことある?たくさん混ぜると白くなる!#ねり飴#駄菓子 ♬ вы милые – я очень устала
ねりあめの魅力は、この変化の過程にあります。

他の飴菓子と異なり、練り飴は食べる人が自ら手を加えることで、その最終形態を創り上げられるのです。
ねりあめの種類と最終形態
ねりあめには様々な種類があります。 水飴や砂糖をベースとしたものだけではありません。
黒糖や蜂蜜、果物などを加えたものなど、風味や色も多岐に渡り、それぞれに個性的な最終形態を見せてくれますよ。
| 種類 | 特徴 | 最終形態 |
| 水飴 | 無色透明で、クセのない甘さが特徴。 | 白く硬くなり、ねっとりとした質感になる。 |
| 砂糖 | 水飴に砂糖を加えて甘さを調整したもの。 | 水飴と同様の変化を見せる。 |
| 黒糖 | 黒糖を加えた、コクのある甘さが特徴。 | 茶褐色になり、やや硬く、ざらりとした舌触りになる。 |
| 蜂蜜 | 蜂蜜を加えた、まろやかな甘さが特徴。 | 黄褐色になり、ねっとりとした柔らかな質感になる。 |
| 果物 | 果汁や果肉を加えた、フルーティーな甘さが特徴。 | 果物の種類によって色や硬さが異なり、果肉が残る場合もある。 |
最終形態でのねりあめの味や食感
練ることで飴の分子構造が変化し、なめらかでしっとりとした食感が生まれます。練る時間や温度によっても質感や風味が変わり、練るほどに上品な甘さが際立ちますよ。
味の進化
練ることで飴に空気が含まれて口当たりがまろやかになり、トロトロの水飴から食べる飴へと進化します。この過程は、ぶどう糖とでん粉の相互作用によるものです。
ねりあめを練りすぎるとどうなる?
お伝えしたとおり、ねりあめの最終形態はあめを練り続けることで白く変化し、空気を含んで硬くなった状態です。
もし、ねりあめを練りすぎるとどうなるでしょうか? 捉え方によっては練りすぎた状態こそが、最終形態だとも考えられますよね。その答えがわかる動画をご紹介します。
詳しい内容は動画で確認してほしいのですが、大きな変化はないみたいですね。
保存方法と最終形態の変化
ねりあめの保存方法によって、最終形態のできは大きく変化します。
高温多湿を避けよう
ねりあめは高温多湿の場所に置くと、溶けたりベタついたりして、本来の食感が損なわれることがあります。そのため直射日光を避け、涼しい場所に保管することが大切です。
密閉容器に入れる
ねりあめは空気に触れると、乾燥したり硬くなったりすることがあります。開封後は密閉容器に入れて保管することで、風味を保ち望ましくない変化を防げますよ。
あなただけの「最終形態」を探求してみませんか?
ねりあめの奥深い世界、いかがでしたか?記事を読んで「自分も最終形態を目指してみたい!」と思った方もいるかもしれませんね。

最近ではソーダ味やフルーツ味など、色や味が変化する楽しいねりあめもたくさんあります。
ぜひお気に入りの一品を見つけて、心ゆくまで練り上げ、あなただけの究極の最終形態を完成させてみてください。
>> Amazonで「味が変わる!?不思議なねりあめセット」を見てみる
ねりあめ最終形態まとめ
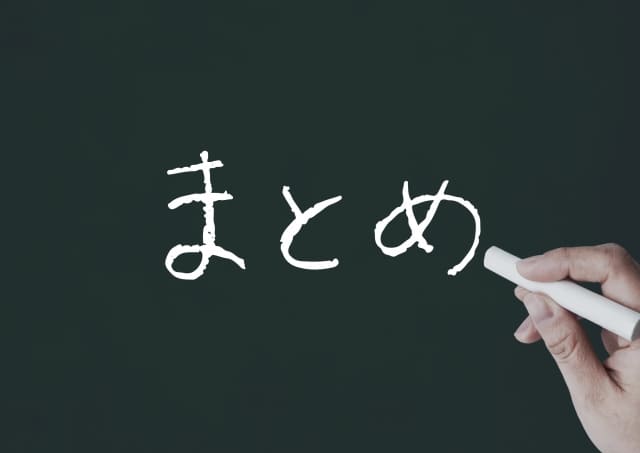
ねりあめは単なる駄菓子ではなく、江戸時代から続く日本の伝統的なお菓子です。その製法や練ることで白くなる仕組み、そして最終形態に至るまでの変化はまさに化学反応そのもの。(笑)
子どもの頃に味わった懐かしさだけでなく、大人になった今だからこそ理解できる奥深い魅力に満ちています。この記事を通して、ねりあめの新たな一面を発見していただけたのではないでしょうか。
保存方法にも気を配りながら、あなただけの「最終形態」を追求し、ねりあめの魅力を存分に味わってみてくださいね。